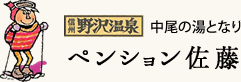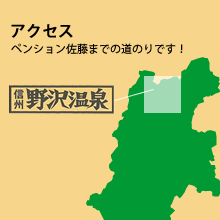季節の便り | 山の幸
2020年05月18日
早々と山へ竹の子採りに。[山の幸]
2020年04月22日
春の山菜採り。[山の幸]
2020.4月
今シーズンは暖冬で、過去に例がない位の
雪不足でした。
あっという間に雪がなくなり、山々の山菜が
かなり早くに大きくなっているとのこと...。
例年では時期的にどうかな?と思ったのですが
友達と一緒に「こごみ」を採りに行ってきました。
良いものが所々に生えていますね。
少し早いようですが十分です。
雨が降ってきたので、直ぐに自宅へ。
まだまだ寒いです。
家に帰り細かいごみを取っていると、
上部の方が茶色く変色したものが
ちらほらと見つかります。
これは霜にあってダメなもの。
よーく選別してから源泉の麻釜へ茹でに
行ってきます。
大釜(熱湯)へ入れて、数分間。
この後、冷水でしっかりと冷やします
温泉で茹でると、風味が良くなるように
感じますね。
我が家のお客様にも好評です。
2019年06月30日
「根曲竹」の竹の子。[山の幸]
2019.6月
野沢温泉では6月に入ると、竹の子の
話題で持ち切りです。
温泉へ行って...。
「山へ行ってきた?」「竹の子どう?」
「全然小さくてダメ」「まだ沢には雪があるし」
こんな感じです。
みんな竹の子が、楽しみで楽しみで。しょうがないんです。
私も6月中旬から下旬にかけて、竹の子採りへ
いってきました。
一回目
二回目
三回目

時期的には遅い感じです。
他の人が採った後で、上物はあまり残って
いませんでした。
個人的に今年は当たり年!!
新しい山菜リュックが大活躍です。
山から戻って、竹の子の皮むきと節ぬきです。
これが一仕事。
柔らかくて美味しそうですね。
源泉の「麻釜」へ。
野沢温泉の6月から7月は竹の子の季節。
みんな楽しみにしているのです。
今晩は定番の「竹の子汁」
もちろん、サバの水煮缶で作ります。
2018年06月17日
今年も竹の子採りに行ってきました。[山の幸]
2018.6/16
竹の子採りの季節がやってきました。
ですが、今年は大問題が発生!
野沢のやまびこゲレンデ付近から奥は、林道の
土砂崩落で通行止めなんです。
やまびこの道路ゲートが閉じられていて、奥山には
入れない状況に...。
竹の子ポイントは人それぞれありますが、皆が困った状況に
なっています。
救済措置というか、6/8頃から10日間ほど木島平側のカヤノ平
高原ゲートを開けて入山が可能になりましたが、一部区間のみです。
この状況下、一部の山へ大勢の人が殺到して大騒ぎ。
まさに早い者勝ち...。
ということで、朝4時出発で山へ。
今日の収穫です。運よく良いポイントへ行けましたね。
時期が早いかもと心配でしたが、十分に採れました。
出始めの小さい竹の子が一杯ありましたが、明日で
ゲートは閉鎖。
あと数日すれば沢山採れるのに...。
残念ですが、しょうがないですね。
皮をむいて節をぬき、柔らかい部分の竹の子を
源泉の麻釜で軽く茹でます。
野沢弁で言うところの「竹の子を殺す」。
物騒な言い方ですが、温泉で茹でることで
風味が増して美味しくなるんですよ。
隣のおじさん(地元の人)は、かごに入れて茹でて
いました。
このやり方は初めて見ました。ちょっとびっくりです。
茹でた後は、水でしっかりと冷やしてから加工工場へ。
保存用にびん詰めや缶詰にします。
今年の初物だから、何の料理にしましょうか?
夕食は、サバ缶の竹の子汁と玉子とじで旬の味を
楽しみます。
藪こぎで重労働な竹の子採りですが、
とっても美味しいので苦労も吹っ飛びますね。
2018年04月30日